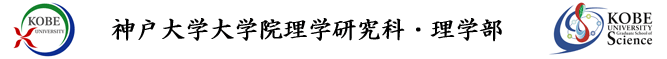News Release
2020.05.18
化学専攻の秋本誠志准教授,植野嘉文研究員らのグループによる研究の成果「IsiAタンパク質に囲まれたシアノバクテリア光化学系Ⅰの構造」がCommunications Biology誌に掲載されました.
シアノバクテリアは地球最古の酸素発生型光合成生物です。一部のシアノバクテリアは,鉄が欠乏した環境下で,光化学系Ⅰ(PSI)の周りに IsiA (iron-stress induced protein A)と呼ばれるタンパク質を発現しますが,この機能については詳細が不明でした。 岡山大学、理化学研究所、筑波大学、神戸大学の共同研究グループは、シアノバクテリアThermosynechococcus vulcanusから単離したPSI-IsiAについて, クライオ電子顕微鏡*1 を用いて構造を,超高速時間分解蛍光分光法*2 を用いて機能を調べました。18個のIsiAがPSI三量体の周りを取り囲み閉じたリング上の構造をしていること, IsiAはPSIに太陽光から得たエネルギーを伝達する機能を持つことを明らかにしました。 本研究成果は、5月11日にCommunications Biology誌に掲載されました。 詳しくは、こちらをご覧ください。
- *1 クライオ電子顕微鏡
- 液体窒素温度でタンパク質粒子を観察する電子顕微鏡のことです。サンプルへの電子線ダメージを軽減するために液体窒素温度での測定を行います。多数のタンパク質粒子の形状を計測して平均化することで、当該タンパク質の立体構造を解析します。2017年にはノーベル化学賞を受賞した技術です。
- *2 超高速時間分解蛍光分光法
- フェムト秒(10-15秒)からピコ秒(10-12秒)の時間分解能を持つ蛍光分析法。光エネルギーを吸収した直後の色素分子の挙動だけではなく,分子が置かれた環境に関するさまざまな物理化学的情報を解析するための非常に有用な分光法です。