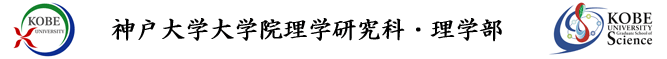理学部・理学研究科の強み・特色
1.他大学・他学部にない独自性(強み)
- ミッション再定義に基づく理学部・理学研究科の独自性(強み)
- 神戸大学の基礎・教養教育の中核としてのはたらき
- 新たな素粒子の発見をはじめとする自然科学分野の世界的に優れた研究を展開
■ 数学専攻 ■ 物理学専攻 ■ 化学専攻 ■ 生物学専攻 ■ 惑星学専攻 ◆ 理学研究科
ミッション再定義に基づく理学部・理学研究科の独自性(強み)
理学部・理学研究科は、グローバルな先端研究の推進を図りつつ、自然科学分野の探求と創造に寄与する人材養成を行い、世界的水準の学術研究に寄与することを目指して教育研究に取り組んでおり、以下の強みや特色、社会的な役割を有している。
- 世界に開かれた国際都市神戸に立地する大学として、幅広い知識と高い専門性を有し、学際的視野、豊かな創造性・国際性、課題探求能力を有する高度専門職業人の育成の役割を果たすとともに、高度な研究能力を持つ先導的な人材の育成の役割を果たす。
- 理数系共通教育の中核を担いつつ、体系化されたカリキュラムによる少人数精鋭教育を実施している。分野横断的科目の実施と国際的な研究連携を活かし、グローバルに活躍できる理系人材を育成する学部・大学院教育を目指してさらなる改善・充実を図る。
- 代数幾何と可積分系、数学計算プログラム、電子型ニュートリノ出現現象、LHC加速器ATLAS実験によるヒッグス粒子発見、多極子伝導系の物理、分子レベルでの音の影響、イオン液体、アミロイド線維、植物の発生成長、RNA生物科学、DNA損傷・修復、地磁気逆転、マグマ活動、星間物質の進化と衝突実験、等の学術的価値の高い特色ある研究を行い、国際的に高い研究水準を維持するとともに、分野を越えた融合研究を推進する全学協力体制も活かし、理学分野の優れた研究の発展と新規領域の開拓により、世界トップを目指す研究を推進する。さらに、3つのグローバルCOE研究を継承しつつ、欧州合同原子核研究機構、国際宇宙科学研究所、海洋研究開発機構、あるいは国内外の大学・研究機関との連携を推進し、アジア・世界における理学分野の研究ネットワークの拠点をめざす。
- 模擬授業、サイエンスセミナー、関西科学塾等の連携活動を通じ、中高生・市民の理学系学問への関心を高めるとともに、理学系教員の輩出により、理学系教育の高度化に寄与する。さらに地域企業との共同研究の推進等により、地域産業界の高度化・活性化に寄与する。
- 企業等に在職のまま博士後期課程へ入学を希望する社会人を受け入れており、社会人の学び直しを推進する。
神戸大学の基礎・教養教育の中核としてのはたらき
(以下、太字の事項は上記の「ミッション再定義」においてエビデンスとして引用した事項を示す。)
理学部・理学研究科の教員は、神戸大学11学部に毎年入学する2,700人を超える学生に対する数学および理科分野の基礎・教養教育を担当する教育部会の中核をなしている。現代社会が科学技術を基盤として動いていることから、数学および理科分野の基礎・教養教育は理系学部学生のみならず人文社会系学部学生にとってもきわめて重要であり、その中核組織としての理学部・理学研究科は神戸大学にとって必要欠くべからざる部局である。
また、理学部・理学研究科における教育は、教員数110人余りに対して学部入学定員が140人、大学院博士前期課程入学定員が120人、博士後期課程入学定員が29人と比較的少人数で実施されており、卒業・修了者は理学分野で共通する論理的な思考力や問題解決能力を身に付ける。このような能力は社会のあらゆる場面で必要とされるものであり、このため、卒業・修了者の職種は、理学各分野の基礎知識や応用力が活かせる中学・高校および大学の教員、公的研究機関や民間企業等の研究開発・技術職にとどまらず、公務員や一般企業の営業職など多様であり、この点は神戸大学の他学部にはない特色である。
新たな素粒子の発見をはじめとする自然科学分野の世界的に優れた研究を展開
理学部・理学研究科における研究活動は非常に活発であり、学術上きわめて重要な研究も多い。以下に理学5専攻の最近の研究活動を紹介する。
■数学専攻
齋藤政彦教授は、研究代表者として大型研究プロジェクト「代数幾何と可積分系の融合と新しい展開」基盤研究(S)(平成19(2007)~23(2011)年度)、「代数幾何と可積分系の融合と深化」基盤研究(S)(平成24(2012)~28(2016)年度)、および「代数幾何と可積分系の融合 - 理論の深化と数学・数理物理学における新展開 -」基盤研究(S)(平成29(2017)~令和3(2021)年度)を推進している。これらのプロジェクトに基づく論文発表や研究集会開催等による当該分野への貢献は、国際的に高く評価されている。前川泰則准教授(現・京都大学准教授)による非圧縮性粘性流体におけるBurgers渦の研究は、従来の摂動論的解析を超えて、大きな渦Reynolds数あるいは非軸対称パラメータの場合を解明した画期的成果であり、平成21(2009)年第26回井上研究奨励賞を受賞した。また、先行する関連研究により2008年度日本数学会建部賢弘奨励賞も受賞している。W.Rossman教授、佐治健太郎准教授(他3名)による双曲的3次元空間における曲面の研究は、与えられた特異点の特異点型について従来にない簡潔な判定条件を与えた。この結果は、多数引用されるなど国際的に高く評価されており、様々な応用や拡張などその後の研究にも大きな影響を与えている。吉岡康太教授(他1名)による4次元ゲージ理論のインスタントン・モジュライ空間の研究は、表現論や幾何学など純粋数学における重要性は言うに及ばず、弦理論をはじめとする数理物理学の先端的研究においても本質的かつ画期的な成果として多数引用され、国際的に極めて高く評価されている。高山信毅教授はD加群計算などの高度な数学計算プログラムを開発・実装し、関連する数学研究の進展に大きく貢献している。野呂正行教授(現・立教大学教授)は数式処理ソフトウエアRisa/Asirの開発・公開を通して、グレブナー基底計算の効率化などで顕著な成果をあげている。両者が参加するプロジェクト"KNOPPIX/Math"は,数学研究者の枠に留まらず広く関心を呼んでいる。
■物理学専攻
物理学専攻は、研究分野ごとに分類した3つの大講座で構成されている。それらは、物理学を理論的な側面から探究する理論物理学講座、自然界の最も基本的な構成粒子=素粒子の性質を実験的に研究する粒子物理学講座、我々の身のまわりの物質が示すさまざまな物理的性質を実験的手法により研究する物性物理学講座の3講座である。
理論物理学講座では、早田次郎教授が第21回日本物理学会論文賞を受賞した。また、播磨尚朝教授の研究論文がJPSJ注目論文として2010年3月と4月、および2018年10月と2019年3月にそれぞれ選出された。さらに、2015年度には、播磨尚朝教授を領域代表として新学術領域研究「J-Physics:多極子伝導系の物理」が発足し、今後の物性物理学研究のより一層の発展が見込まれる。播磨尚朝教授は、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度に神戸大学学長表彰を受けた。野海俊文准教授(2023年度に異動)は、2017年度に第12回日本物理学会若手奨励賞を受賞し、2020年度に第15回素粒子メダル奨励賞および神戸大学優秀若手研究者賞・理事賞を受賞した。
粒子物理学講座が参画する長基線ニュートリノ振動実験T2K実験グループは、2011年6月に世界で初めての電子型ニュートリノ出現現象の兆候を報告し、2013年7月にその後に得られた3.5倍のデータを加えて、この転換過程が確かに存在することを確立しました。また、粒子物理学講座が参画する、世界最大の加速器LHCを用いたATLAS実験グループは2012年7月に新粒子発見の兆候を報告し、その後ヒッグス粒子と断定され、素粒子物理学史上の大きな発見の1つとなった。この成果により、ATLASグループは2013年の学長表彰を受賞した。2015年度には、ニュートリノ振動発見の業績により、粒子物理学研究室の24名の所属者・出身者に対して、2016年基礎物理学ブレークスルー賞が授与された。2017年度にはニュートリノ実験グループと身内賢太朗准教授が、2018年度には身内賢太朗准教授と越智敦彦准教授が、2020-2023年度には身内賢太朗准教授が、2022年度には鈴木州助教(当時)が,それぞれ神戸大学学長表彰を受けた。2022年度には、藏重久弥教授らの参加するGeant4日本グループが高エネルギー加速器科学研究奨励会・諏訪賞を受賞した。
物性物理学講座では、太田仁教授が、2008年にInternational EPR/ESR Society (IES) Silver Medal 2008 for Instrumentationを、2019 年に国際ザボイスキー賞を受賞した。また、2008年以後、物性物理学講座所属教員により、以下の論文選出や受賞がある。松岡英一准教授は第2回日本物理学会若手奨励賞を受賞した。大道英二准教授は第5回日本赤外線学会奨励賞、第3回日本物理学会若手奨励賞、電子スピンサイエンス学会奨励賞を受賞している。菅原仁教授は第15回日本物理学会論文賞を、小手川恒准教授は第7回日本物理学会若手奨励賞を受賞した。また、2014年度に小手川准教授・藤教授・菅原教授らがCr系で初めての超伝導を圧力下発見し、JPSJの注目論文に選出された。2016年度に、大久保晋准教授と太田仁教授が日本赤外線学会・第2回学会誌論文賞を受賞した。2018年度には、櫻井敬博助教、大道英二准教授、太田仁教授らが日本赤外線学会・第4回学会誌論文賞を受賞し、高橋英幸助教が日本赤外線学会・第5回研究奨励賞を受賞した。高橋英幸助教は、2019 年度に電子スピンサイエンス学会・奨励賞と神戸大学優秀若手研究者賞・理事賞を受賞し、2019年度と2020年度に神戸大学学長表彰を受けた。2021年度には、太田仁教授が日本赤外線学会・第6回業績賞を受賞し、大久保晋准教授と太田仁教授が日本赤外線学会・第7回学会誌論文賞を受賞、小手川恒准教授が日本物理学会・第27回(2022)論文賞を受賞した。また2024年2月には,小手川恒准教授、藤秀樹教授、菅原仁教授の共著論文が第29回(2024)日本物理学会論文賞を受賞した。
■化学専攻
化学専攻は無機化学・有機化学・物理化学という研究分野を横糸とし、物質合成や物質解析などの研究手法を縦糸とすることによって専攻内外との共同研究を活性化することをめざしている。化学における一般性と特殊性のバランスを保ちながら、新しい概念の創出につながる学際領域の開拓を進めている。 秋本誠志教授は光合成タンパクの機能解析に関して、内外から注目される研究成果を多数挙げてきた(Nat.Commun.2023、e-life 2022、Nat.Commun.2022、Nat.Commun.2022)。高橋一志准教授は鉄錯体のスピンクロスオーバー現象を利用して分子間相互作用の役割に関する新たな知見を見出した(Nat.Commum.2024)。持田智行教授は金属錯体を液化する斬新な研究を展開してきた。富永圭介教授はテラヘルツ光を使った分光計測により、蛋白質の一種であるバクテリオロドプシンが水とゆるく結合した水和状態でのみ蛋白質としての機能が発現する温度において熱的に活性化されることを明らかにした。 津田明彦准教授は二重らせん構造を持つDNAが液体の渦の流れに沿ってらせん状に配向する現象を見出し、さらに右巻きの二重らせん構造を持つDNAが、左巻きのDNAよりも右巻きの渦を好んでらせん配向することを明らかにした。茶谷絵理准教授は、神経変性疾患の発症に深く関わるオリゴマーやプロトフィブリルの形成過程を捉え、これらがサイズと構造を発達させながらアミロイド線維が生成する様子を明らかにした。松原亮介教授は、遷移金属を用いることなく光エネルギーで二酸化炭素を資源化する触媒系を開発した(Nat.Chem.2023)。炭素循環社会実現への貢献が期待される。 大西洋教授は、不凍液に浸した氷の表面形状を冷却ボックスで冷やした原子間力顕微鏡を使って精密に計測し、高さが0.1 nm(髪の毛の太さの百万分の一)の階段状の構造が氷表面に発生することを見いだした(J.Chem.Phys.2024)。このような計測の応用範囲を広げることで、氷のサイエンスとエンジニアリングを進展させることが期待できる。小堀康博教授は、励起子ペアとよばれる高いエネルギーを持つ特殊な中間体からエネルギー変換を起こす機構の解明を行った。時間分解電子スピン共鳴法を用い、励起子ペアがスピン変換、励起子間の解離や光アップコンバージョンを起こす中間状態の立体構造と活性化分子運動の詳細を示した(J.Phys.Chem.Lett.2024、Sci.Adv.2024、Angew.Chem.Int.Ed.2024、Nat.Commun.2023、Angew.Chem.Int.Ed.2023、ACS Energy Lett.2022)。さらに、光受容クリプトクロムによる磁気コンパス機構に関する記事が月刊「細胞」で紹介された(2023)。立川貴士教授はメソ結晶光触媒等の研究で顕著な研究成果を挙げている(Nat.Commun.2022)。木村建次郎教授は、対象領域すべてを可視化する散乱場理論を確立した。対象領域に淵から波動を照射し、跳ね返ってきた波動の観測結果から対象領域内の構造を可視化する問題は、未解決問題として知られていた。この問題に対して基礎方程式とその解析解の導出を行い、対象領域すべてを可視化する理論を確立した。この成果は物質内部の可視化技術として実用化され、多数報道されている。
■生物学専攻
生物学専攻では3講座体制で、モデル種から希少種に至る多様な生物を用いて分子・ゲノム・細胞などのミクロレベルから個体・集団・生態系などのマクロレベルまで幅広くカバーした研究を行い、国際的に優れた特色ある研究成果を継続的にあげている。生体分子機構講座は、動物の神経・行動や植物の環境応答・成長発生に関する生理機能の研究を特色とし、最近は、尾崎まみこ教授らによる昆虫の味覚と嗅覚を司る感覚神経の相互作用に関する研究(Chemical Senses, 2014)や社会性昆虫における個体間コミュニケーションにおける化学感覚タンパク質の研究(Scientific Reports, 2015)、昆虫の飢餓ストレスによる行動異常の研究(Scientific Reports, 2017)を進め、北條特命助教は第25回吉田奨励賞(日本比較生理生化学会、2016年9月)を受賞した。さらに佐倉緑准教授による昆虫の経験に基づく行動変容とその神経機構の研究(日本比較生理生化学会、第23回吉田奨励賞受賞、2014年10月)のほか、脳神経の働きや修復を支える分子・細胞機構の研究が進められている。また、三村徹郎教授らの植物の物質代謝や運搬・貯蔵の研究(Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2016)、洲崎敏伸准教授らによる原生生物や共生微生物の研究などを基礎に、東北大震災後の土壌や水質の調査・回復の研究にも大きく関わっている。洲崎准教授は医学生物学電子顕微鏡技術学会・学会賞(2016)と功労賞(2018)を受賞した。さらに、深城英弘教授らによる植物の根の成長発生の機構に関する研究(Development 2012, 2016;Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2016, 2019;Science, 2018;Developmental Cell, 2018;New Phytologist 2019)、
石崎公庸教授らによる、ゼニゴケを用いた陸上植物における発生制御機構進化に関する研究(Nature Plants 2020; Current Biology 2019, 2019, 2018, 2016; Nature Communications 2018, 2014;)(日本植物生理学会奨励賞受賞、2015年3月;日本植物学会Journal of Plant Research Best Paper賞受賞,2013年9月)、およびゼニゴケ全ゲノムの解読・解析に成功した国際共同研究(Cell, 2017)、近藤侑貴准教授らによる維管束の細胞分化制御機構に関する研究(Communications Biology 2020
;Plant Cell 2021)、宮本昌明教授らによる線虫における低分子Gタンパク質のシグナル伝達に関する研究(Development, 2013)など、興味深い成果が得られている。
近藤侑貴准教授は、日本植物学会奨励賞(2021)、令和4年度文部科学大臣表彰若手科学者賞(2022)を受賞した。
生命情報伝達講座では、動物の発生制御や細胞情報伝達の分子機構を中心に研究を行っている。最近では、影山裕二准教授らによる小さなペプチドを介した時期特異的な遺伝子発現制御に関する研究(Nature Cell Biology, 2014)や幹細胞の細胞死抑制と増殖促進の分子機構の研究(Nature Communications, 2018)、坂本博教授らによる神経の発生と可塑性に重要なRNA結合蛋白質HuDの特定と作用機序の研究(Molecular Cell, 2009)、井上邦夫教授らによるマイクロRNAによる翻訳抑制機構に関する研究(Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2011)、
松花沙織助教らによる心臓神経堤細胞形成に関する研究(Developmental Biology 2019)、
鎌田真司教授らによる細胞老化の研究(Scientific Reports, 2016)が進められ、菅澤薫教授らによる紫外線によるDNA損傷の認識と修復に必須のユビキチンリガーゼ複合体の構造と作用機序などの研究(Cell, 2011; Nucleic Acids Research, 2015)、紫外線により染色体DNAに発生した損傷を検出するメカニズムの研究(Nature, 2019)が相次いでトップジャーナルに掲載され、菅澤薫教授は第4回アジア・オセアニア光生物学会の学会賞(2019年8月)を受賞した。
また岩崎哲史助教は、ホルボールエステルによる転移性メラノーマの増殖抑制の分子機構に関する研究で日本色素学会奨励賞(2019年11月)を受賞した。
さらに、受精・発生過程や癌化等における、転写制御の研究や、蛋白質リン酸化やアポトーシスに注目したシグナル伝達の研究が進められ、国際会議や国際誌で多くの発表がなされている。
生物多様性講座は、水生生物の系統分類や進化、生態の研究を特色としている。これまで、村上明男准教授らによる光合成藻の新規光センサー蛋白質複合体の構造と機能の解明(Nature, 2002)、60年来疑義の絶えなかった“真正紅藻の第二の葉緑素”がシアノバクテリア由来であることを証明した研究(Science, 2004)、川井浩史教授らによる多細胞海藻類初の全ゲノム解読・解析に成功した国際共同研究(Nature, 2010)などエポックメーキングな成果を出しており、川井教授は日本藻類学会学術賞(2019年3月)を受賞した。佐藤拓哉准教授は寄生生物ハリガネムシが森林生態系と河川生態系の物質循環をつなぐ重要な役割を果たしていることを明らかにし、国外の生態学の教科書で紹介されたほか、「信州フィールド科学賞」(2013年11月)と優れた若手生態学研究者に与えられる日本生態学会「宮地賞」(2014年3月)を受賞した。ハリガネムシ類に寄生されたカマキリが自ら川や池に飛び込む仕組みの一端を解明した研究(Current Biology 2021)も進められた。小菅桂子准教授らによる水草の分子生態学の論文が、日本植物学会Journal of Plant Research Best Paper賞(日本植物学会,2017年9月)を受賞した。末次健司准教授(2022年10月より卓越教授)は、従属栄養植物の生態、分類研究で顕著な業績をあげ「ナイスステップな研究者2016」(文部科学省科学技術・学術政策研究所)に選ばれるとともに、文部科学大臣表彰(若手科学者賞)(平成30年度科学技術分野)、第28回松下幸之助記念奨励賞を受賞している。希少種を含む水生植物が体系的に研究されており、坂山英俊准教授らによる陸上植物に近縁なシャジクモ類の全ゲノム解読(Cell, 2018)や藻類における新たな遺伝子獲得が陸上植物の配偶子形成機構に結びついたとの研究(Nature Communication, 2018)が進められた。多様性保全への寄与なども期待されており、角野康郎(名誉)教授が、第26回 松下幸之助花の万博記念賞 松下幸之助記念賞の受賞者として、保全生態学の普及に大きな貢献をした功績が評価されている(2017)。
■惑星学専攻
平成27(2015)年4月、地球科学と惑星科学・宇宙科学の融合を促進するより包括的な教育研究の展開を目指して、従前の地球惑星科学専攻(学科)を改組し、他には例のない名称である「惑星学専攻(学科)」へと改名した。「なぜこの星は地球なのか?」を副題に掲げ、太陽系の形成と惑星地球に至る進化、様々な変遷を経つつも今日に至るまで表層に液相の水を貯え生命をはぐくむ環境を維持してきた水惑星地球の歴史と安定性、将来のあり得る姿の予測、こういった問題に取り組み、海洋・宇宙立国をリードする人材の育成のため「見識を備えた有識者」と「独創的研究者」の育成を行う。
近年の研究成果は、最近における特記事項を参照。
◆理学研究科
上記のような国際的に評価される活発な研究活動に伴って、理学部・理学研究科は多くの外部研究資金を受け入れており、関連学内研究センターを除いた理学部・理学研究科本体が獲得した科研費は平成22(2010)-26(2014)年度の5年間で総額1,644,157千円(年度平均で約3億3千万円)、またその他の受託研究等の外部研究資金は平成21(2009)-25(2013)年度の5年間で総額719,006千円(年度平均で約1億4千円)に上る。特に、科研費については教員1人当たりで年間約340万円獲得していることになり、この数字は神戸大学内においてはトップレベルである。また、以下のように5専攻の中で3専攻がグローバルCOE研究に参画した。数学専攻:「マス・フォア・インダストリ教育研究拠点」(平成20(2008)-24(2012)年度)、生物学専攻「統合的膜生物学の国際教育研究拠点」(平成19(2007)-23(2011)年度)、地球惑星科学専攻「惑星科学国際教育研究拠点の構築」(平成20(2008)-24(2012)年度)。
一方、理学部・理学研究科の教員のおよそ半数がそれぞれの分野の専門家として、文部科学省、日本学術振興会、地方自治体、民間研究助成財団等における各種の審議会、審査会、評価委員会等の委員として活動しており、社会的にも大きく貢献している。
[ 自己評価委員会 ]