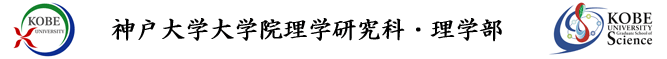News Release
2025.01.24
生物学専攻の末次健司教授は、牧野富太郎が発見し新属として記載した「コオロギラン」の生態を調査し、その属名の由来となった指状の付属物が受粉の上で重要な役割を果たしていることを明らかにし、国際誌「Plants, People, Planet」に発表しました。
コオロギランは、著名な植物学者である牧野富太郎が発見した植物であり、柱頭(stigma)の下にある指状(dactyliform)の付属物にちなんで新属「Stigmatodactylus」と名付けられました。
しかし、この属名の由来となった指状の付属物の生態的意義は、130年以上にわたり不明のままでした。
本研究では、この長年の謎に焦点を当て、指状の付属物が果たす生態的役割を解明することを目的に研究を行いました。その結果、コオロギランの花が咲いてからおよそ3日後にこの付属物が倒れることが確認されました。この変化により花粉塊と付属物が接触し、付属物を経由して花粉管が伸長することでコオロギランは実をつけることができることが明らかになりました。コオロギランは、牧野富太郎が発見した植物の中でも特に代表的なものであり、NHK朝ドラ「らんまん」の週タイトルにもなった有名な植物です。本研究は、牧野が注目したにもかかわらず100年以上その機能が不明のままであった構造が、実際に重要な意義を持っていたことを示しています。
さらに、本研究は、分類学の際に重視された構造を詳細に調査することが、生物の生態に対する洞察を深めることを強調しています。現代では、分類学と生態学は別々の研究者によって進められることが一般的ですが、本研究は、分類学、進化学、生態学が一体となった昔ながらの自然史研究が、現代でも新たな現象を解明する力を持つことを証明しています。
本研究成果は、1月24日午前0時(日本時間)に国際誌「Plants, People, Planet」に掲載されました。 詳しくはこちらのページをご覧ください。